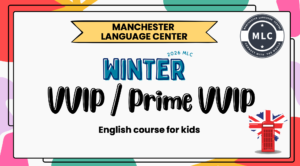マレーシアへの移住やビジネス展開を検討する際、税金制度の理解は欠かせません。所得税や法人税の税率、日本との違い、二重課税の回避方法などを知らずにいると、思わぬ税負担が発生する可能性も。本記事では、マレーシアの税制の基本から、個人・法人向けの税率、節税対策、申告手続きの流れまで詳しく解説します。さらに、日本との租税条約を活用した節税方法や、信頼できる税理士の探し方についても紹介。正しい知識を身につけ、賢く税務管理を行いましょう。
目次
マレーシアの税制の基本概要

マレーシアの税制の基本となるポイントは以下のとおりです。
上記のポイントを以下で詳しく解説します。
マレーシアの税制度の特徴とは?日本との違いを解説
マレーシアの税制度は、日本と大きく異なります。まず、所得税は累進課税ですが、最高税率は30%と日本(45%)より低め。さらに、海外所得は原則として非課税で、海外移住者にとって魅力的な税制です。法人税は一般企業で24%、中小企業には軽減税率が適用され、ビジネスのしやすさが特徴。消費税(GST)は2018年に廃止され、現在はSST(セールス&サービス税)が導入。サービス税は2024年3月1日から多くの対象が8%、飲食・通信・駐車・物流などは6%据え置き。日本との二重課税を防ぐ租税条約もあり、適切な税務管理が重要です。
マレーシアの主な税金の種類(所得税・法人税・消費税など)
マレーシアの税制には、主に所得税・法人税・消費税(SST)の3つがあります。所得税は累進課税で、個人の課税所得に応じて0~30%の範囲で適用。非居住者は一律30%と高めです。法人税は一般企業で24%、中小企業(SME)は最初の60万リンギまで17%の優遇税率が適用されます。2018年に廃止された消費税(GST)の代わりに、現在は6〜8%の売上税・サービス税(SST)が導入され、特定の取引やサービスに課税されます。これらの税制を理解し、適切な対策を講じることが、マレーシアでの資産管理やビジネス成功の鍵となります。
マレーシアの税率はどのくらい?個人・法人の税率一覧
マレーシアの税率は、個人と法人で異なります。個人所得税は累進課税で、年間所得5,000リンギ以下は非課税、最高税率は30%(年間所得200万リンギ以上)です。一方、非居住者は一律30%の税率が適用されます。法人税は一般企業で24%、中小企業(SME)は最初の60万リンギまで17%、それ以上は24%となります。さらに、特定の業種や地域では税制優遇措置が設けられています。これらの税率を把握し、適切な税務対策を行うことで、マレーシアでの個人資産管理や事業運営をより有利に進めることが可能です。
マレーシアの個人所得税の仕組み

マレーシアの個人所得税の仕組みのポイントは以下があげられます。
上記のポイントを把握していると、マレーシアの個人所得税を把握できます。
所得税の課税対象となる収入の種類
マレーシアの個人所得税は、国内で得た収入に対して課税されます。課税対象となる主な収入には、給与所得、事業所得、賃貸収入、利子・配当収入、ロイヤリティ、年金などが含まれます。特に、給与所得は源泉徴収されるため、雇用主が税務当局に納税を代行します。一方、賃貸収入や事業所得は自己申告が必要です。非課税となる収入もあり、例えば海外からの所得は原則非課税です。ただし、最新の税制改正により、一定の条件下で海外収入にも課税されるケースがあるため、最新の情報を把握することが重要です。
所得税の計算方法と控除の種類(住居費・教育費など)
マレーシアの個人所得税は、累進課税制度を採用しており、課税所得が高いほど税率も上がります。税額は「課税所得=総所得-控除額」で算出され、税率は0%~30%の範囲で適用されます。控除には、個人控除、扶養控除、医療費控除、住居ローン利息控除、教育費控除などがあり、最大限活用することで税負担を軽減できます。特に、住居費や教育費は大きな控除対象となるため、節税を意識した計画が重要です。適用される控除額や計算方法を正しく理解し、適切な税務申告を行いましょう。
居住者と非居住者の税率の違いとは?
マレーシアの所得税は居住者と非居住者で税率が大きく異なるのが特徴です。税務上の居住者は、マレーシアに1年間で183日以上滞在した個人と定義され、累進課税(0%〜30%)が適用されます。一方、非居住者は一律30%の税率が適用され、控除の対象にもなりません。例えば、給与所得の場合、居住者は課税所得に応じた税率で課税されますが、非居住者は無条件に30%課税されます。そのため、長期滞在を計画している場合は、税務上の居住者資格を得ることで節税につながる可能性があります。
マレーシアの法人税の仕組み

マレーシアの法人税の仕組みのポイントは以下があげられます。
上記のポイントを把握していると、マレーシアの法人税に対する理解が深まります。
法人税の基本税率と優遇措置
マレーシアの法人税の基本税率は24%です。しかし、一定の条件を満たす企業には優遇措置が適用されることがあります。例えば、中小企業(SME)に対しては、初めの60万リンギの課税所得に対し、17%という低い税率が適用されます。また、新規事業や特定の業界では税額控除や投資奨励金が提供されることもあります。これらの優遇措置は、マレーシア政府がビジネスの成長を促進するために実施しており、特にスタートアップや新規進出企業には有利な環境です。法人税の計算においては、事業の規模や種類を正確に把握することが重要です。
SME(中小企業)向けの税制優遇措置とは?
マレーシアでは、中小企業(SME)に対して税制優遇措置が多く提供されています。特に、法人税率が軽減される点が特徴です。具体的には、60万リンギまでの課税所得には17%の低税率が適用され、それを超える部分には通常の24%の税率が課せられます。この優遇措置は、中小企業の成長をサポートするために設けられており、企業活動の促進に寄与しています。また、新規事業や特定の業界には、税額控除や投資奨励金も提供され、事業開始時の負担を軽減できます。これらの優遇措置を活用することで、中小企業は競争力を高め、事業の成長に繋げることができます。
税務申告の流れと必要書類
マレーシアの法人税務申告は、年次決算後の申告が基本です。まず、企業は決算日から3ヶ月以内に申告書(Form C)を提出しなければなりません。申告書には、税引前利益や控除対象経費を反映させた税務計算を記載します。次に、必要書類としては、監査済み財務諸表、取引明細書、税務計算書、税務調整明細などが求められます。これらの書類をオンラインで提出することで、税務署(LHDN)に申告を完了させます。税金の支払い期限は申告書提出後、通常30日以内です。適切な申告を行わないと、罰金や追加税金が課せられる可能性があるため、必要書類の準備と提出期限を守ることが重要です。
日本との二重課税を防ぐ方法

日本との二重課税を防ぐ方法は以下の知識が重要です。
上記のポイントを把握していると、日本との二重課税を防ぐ方法がわかります。
日・マレーシア租税条約の概要
日・マレーシア租税条約は、日本とマレーシア間で二重課税を防ぐための重要な取り決めです。この条約により、両国間で発生する税金の二重課税を避けるために、課税権の分配が行われます。例えば、所得税においては、両国がどの国で税金を課すかを明確に定め、居住地国と源泉地国での税務処理方法を整理しています。この条約の主な目的は、税金の二重支払いを防ぐとともに、税務上の透明性を確保することです。また、控除や免税措置を活用することで、税金を軽減することも可能です。日本とマレーシア間でビジネスを行う場合、租税条約を理解し、適切に申告することが、税負担を最適化するために不可欠です。
二重課税の回避方法と手続きの流れ
日本とマレーシア間の二重課税を回避する方法は、租税条約に基づいています。まず、税務申告時に適切な控除や免税措置を適用することが重要です。日本とマレーシアの税務当局に税務証明書を提出することで、源泉税の軽減を受けることができます。次に、外国税額控除の利用がポイントです。これは、マレーシアで支払った税金を日本の税金から控除する方法です。この控除を適用するには、税務申告書に外国税額控除申請書を添付し、マレーシアで支払った税金の証明書を提出する必要があります。これにより、二重に税金を支払うことを防ぎ、税負担を軽減できます。手続きの流れとしては、日本の税務署に申告書を提出後、必要な書類をマレーシアの税務署に確認することが求められます。
日本に納税義務があるケースとは?
日本に納税義務が生じるケースは、日本国内に所得源がある場合です。例えば、日本に不動産を所有している場合、その賃貸収入や売却益は日本で課税されます。また、日本国籍や居住者であれば、世界中の所得に対して日本の税金が課せられることがあります。特に、海外で得た収入が日本で申告義務に該当することが多く、その場合、二重課税の回避措置を利用することが求められます。例えば、給与所得や配当収入が日本の税法に基づいて課税対象となることがあります。そのため、日本に納税義務が生じるかどうかは、居住状況や収入源によって異なり、適切な申告が求められます。
マレーシアでの節税対策と注意点

マレーシアでの節税対策と注意点は以下のとおりです。
上記のポイントを把握していると、マレーシアで適切に節税できます。
海外移住者が活用できる節税のポイント
マレーシアへの海外移住者にとって、節税のポイントは非常に重要です。まず、非居住者税制を活用することで、一定の税優遇が得られます。特に、住居費や教育費などが控除対象となる場合があり、生活費を節税に結びつけることが可能です。さらに、法人税の優遇措置や事業所得の減税も活用できます。特定の投資信託や退職金積立も、税制上の優遇措置を受けられる場合があり、これらを利用することで税負担を軽減できます。とはいえ、居住者と非居住者の税制差を理解し、現地の税務専門家に相談することが重要です。適切な情報を得ることで、税務管理の最適化が実現します。
ビジネスオーナー向けの税制優遇策
マレーシアでのビジネスオーナー向けには、税制優遇策が多数あります。まず、中小企業(SME)向けの法人税優遇があり、これにより税率が低く抑えられます。特に、最初の5年間は法人税の免除や減税措置が適用されることが多く、企業の成長を支援します。さらに、投資税額控除(ITA)や、特定の産業に対する優遇税制(製造業、ハイテク産業など)もあります。これにより、特定の事業活動に対して投資を促進し、税負担を軽減できます。また、事業経費として計上できる費用も広範囲で、適切に申告することで実質的な税負担が減少します。税務計画をしっかりと立てることが、ビジネスの利益最大化に繋がります。
適切な税務対策を行うために気をつけること
マレーシアで適切な税務対策を行うためには、いくつかの重要なポイントを押さえておくことが必要です。まず、税務申告の正確性が最も重要です。申告内容に誤りがあると、罰金や延滞税が課される可能性があるため、正確な記録を保つことが求められます。次に、税法の変更点に注目することです。税制は年々改定されるため、最新の規定を把握し、変更があった場合は速やかに対応することが大切です。また、税務専門家の活用も効果的です。税理士や会計士の助言を受けることで、複雑な税務手続きを正しく進めることができます。さらに、適切な経費の申告も節税に繋がりますが、虚偽の経費申告は厳しく取り締まられるので注意が必要です。
マレーシアの税務申告の手続きと期限

マレーシアの税務申告の手続きと期限は以下がポイントにあげられます。
上記のポイントを把握していると、スムーズに税務申告を行えます。
個人の税務申告の流れと申告期限
マレーシアでの個人の税務申告は、まず申告書の提出から始まります。マレーシアでは、毎年1月1日から12月31日までの期間に得た所得について、翌年4月30日までに申告を行う必要があります。オンライン申告システムが利用できるため、便利に申告を進めることが可能です。申告書を提出する際には、収入証明書や控除証明書などの必要書類を準備することが求められます。次に、申告内容の確認が行われます。申告書提出後、税務署から追加の資料提供を求められる場合がありますので、柔軟に対応することが重要です。期限を過ぎて申告した場合、延滞金や罰金が課せられるため、早めに手続きを完了させることをおすすめします。
法人の決算・税務申告の流れ
マレーシアでの法人の決算と税務申告は、企業の財務状況を正確に反映させる重要な手続きです。まず、会計年度終了後に決算を行い、その決算書類を基に法人税の申告書を作成します。マレーシアでは、法人の税務申告期限は会計年度終了後、3ヶ月以内に提出することが求められます。申告書には、財務諸表や収益明細書を添付し、税務署に提出します。オンラインシステムを活用することで、申告はスムーズに進められます。申告後、税務署が内容を確認し、税額の確定が行われます。万が一、申告に不備がある場合は、修正申告を行い、税務署から指摘を受けた際は迅速に対応することが重要です。申告漏れや期限遅延による罰金を避けるため、規定に従った正確な申告が求められます。
申告漏れ・未納のリスクと対処法
マレーシアでの申告漏れや未納は、重大な税務リスクを招く可能性があります。申告漏れがあると、税務署から追加課税や罰金を受けることになり、最悪の場合、事業運営への影響が出ることもあります。これを防ぐためには、税務申告の期限を守り、正確に情報を報告することが基本です。万が一、申告漏れに気付いた場合は、修正申告を行うことでリスクを最小限に抑えることができます。また、未納分の税金がある場合、早急に納付することが推奨されます。税務署は、未納に対して高額な利息や延滞金を課すことがあり、遅延は企業の財務状況に悪影響を及ぼす恐れがあります。未納の税金がある場合は、納税計画を立てて確実に支払うことが重要です。
マレーシアの税金に関するよくある質問(FAQ)

マレーシアの税金に関するよくある質問は以下のとおりです。
上記の疑問を把握していると、マレーシアでスムーズに税申告できます。
マレーシアの消費税(GST)は現在どうなっている?
マレーシアの**消費税(GST)は、2018年に一時廃止され、代わりにサービス税(SST)が導入されました。GSTは、商品やサービスに対して広範囲で課税される方式でしたが、SSTは主に製造業と小売業に適用される税制です。現在、SSTは6〜8%**の税率で、消費者に影響を与えるのは主に特定の商品やサービスに限られています。たとえば、飲食業や小売業の一部商品に対して課税されるほか、一部の高級商品も対象です。消費税廃止後、マレーシア政府は税制を簡素化することを目指し、SSTの導入で税務運営の効率化を進めています。これにより、企業や消費者にとっても新しい税制度への適応が求められます。
海外収入はマレーシアで課税される?
マレーシアでは、居住者と非居住者で課税の扱いが異なります。居住者(1年間に183日以上マレーシアに滞在する人)については、世界中の収入が課税対象となります。つまり、海外収入もマレーシアで課税される可能性があります。例えば、外国で得た給与や投資収益も課税対象となることがあります。しかし、非居住者の場合、マレーシア国内で得た収入のみが課税対象となり、海外収入には課税されません。重要なのは、日々の滞在状況や収入の種類により税務処理が異なるため、正確な申告が必要です。税制の詳細を理解し、適切な申告を行うことが重要です。
マレーシアで信頼できる税理士・会計事務所の探し方
マレーシアで信頼できる税理士や会計事務所を探す際は、まず実績や評判を確認することが重要です。信頼性の高い事務所は、長年の経験や現地の税法に精通している点が特徴です。具体的には、ウェブサイトやオンラインレビューをチェックして、他のクライアントの評価を参考にしましょう。また、公式認定を受けている事務所は、信頼度が高いので安心です。さらに、事前に無料相談を活用して、税理士の対応や専門知識を確認することも大切です。特に、日本語対応可能な事務所を選ぶと、コミュニケーションがスムーズになります。信頼できる税理士を見つけることが、税務申告や節税対策を成功させる鍵となります。弊社OSBでも税理士や会計士の紹介を行っております。
まとめ|マレーシアの税制を理解して適切な税務管理を!

マレーシアの税制は、移住やビジネス展開を検討する際に重要な要素です。所得税や法人税の税率、二重課税回避方法など、特に日本との違いが重要です。個人所得税は累進課税で、海外所得は非課税が原則。法人税は中小企業向けに優遇措置があり、税率は24%ですが、一定条件を満たす企業には軽減措置が適用されます。また、消費税は廃止され、売上税・サービス税(SST)に変更されました。さらに、日本とマレーシア間での二重課税を防ぐため、租税条約を活用する方法も重要です。
マレーシアの税制について理解し、適切な税務対策を行うことは、移住やビジネス成功のカギとなります。
「マレーシアの税制についてさらに詳しく知りたい」「自分の状況に合った税務アドバイスを受けたい」
そんな方は、OSB EDUCATION へお問い合わせください!